ルーシー・リー展(国立新美術館)
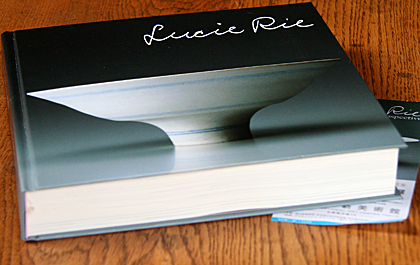
憧れの初恋の人との邂逅のようで、秘めた思いが掻き立てられ、晴れがましくも気持ち高ぶるといった観覧だった。
2003年、ニューオータニ美術館の【「静寂の美」ルーシー・リー展】以来、三度目のルーシー・リー展。
4月からほぼ2ヶ月にわたる会期であったのだが、自分の個展の時期とも重なり、スケジュールが立たず“日に疎し”の状況を呈しつつあった。しかしやはり最終日近くともなれば心落ち着かず、恋い焦がれる如く、強行軍で出掛けた。(相応の所要時間、経費が掛かるのが地方在住の悲しさ)
250点という出展数にも表されているが、国内で開かれるものとしては空前規模の回顧展だと思われ、これだけの充実した内容で観られるのは最後かもしれず、逢えて良かった、というのが素直な心境だ。
凛とした佇まいと、やぼったさとは対極の洗練された華やかさを併せ持つ独特の陶芸世界といったところなどは、ファンならずともその作風を知る人には誰しも共通する評価だろうと思うのだが、しかしどうしてここまで現代の日本人を魅了してやまないのだろうか。
(既に会期を終えた東京展だけでも10万人以上を動員したという)
陶芸と言えば何と言っても日本のものが最高であり、他国の追随を許さないというのが、現代日本の標準的な評価基準であったところへ、1960年代、颯爽と現れたイギリスの女性陶芸家、ルーシー・リーの作品群の紹介は、井の中の蛙の日本陶芸界に衝撃を与えるに十分な“事件”であったというような記事を読んだことがあったが、木工への興味も、陶芸への感心にも“遅れてきたウスノロ青年”でしかなかったボクにとっても、ニューオータニ美術館の【「静寂の美」ルーシー・リー展】観覧は実に衝撃的で陶芸の美質の基準を改められるようなものだった。
ルーシー・リーについては2003年のニューオータニ美術館、および2007年のshizuoka Art Gallery、それぞれ観覧記として記述してきている(1、2)ので、繰り返しは避けたいと思うので、今回の回顧展の特徴などに絞って紹介しておこう。
今回は「没後初の大回顧展」と銘打たれているように企画サイドとしてはかなり力の入ったものであっただろうことを思わせる(企画は東京国立近代美術館)。
 それはまずは展示構成に表されていた。
それはまずは展示構成に表されていた。大きく「初期、ウィーン時代」「形成期、ロンドン時代」「円熟期」と3つの時代に分け、それぞれの時代背景と彼女の作風の変化、それをもたらした関係者との交流などを、それぞれの作品はもちろんとして、釉薬の研究ノート、試料、資料、公的文書、あるいは私信などをふんだんに展示活用させ、創作の謎解きを試みるような内容となっている。
またよく知られるように、ルーシー・リーを日本に本格的に紹介するきっかけとなった三宅一生氏に託された陶器のボタンを、その型を含め、別コーナーとして展示されているのが印象的だった。
ボクは陶芸は門外漢なのでトンチンカンな評価になってしまうかもしれないが、彼女の陶芸を独自の世界たらしめている要因は、あの独特のテクスチャー、色彩、そして造形感覚などいくつもの視点から見ることができると思うのだが、多彩な作風のどれをとっても他の何物でもない、ルーシー・リーその人の作品として自立しているという不思議な世界である。
テクスチャー、色彩ということに絞れば、やはり素焼きせずにろくろ成形した土にいきなり釉薬を塗り(刷毛塗りという独自の手法)、高温で焼成させる手法ならではのものであるようだ。
造形ということにおいては、ロンドン亡命前の「ウィーン工業美術学校」でのヨゼフ・ホフマン、コロマン・モーザーらからのセセッション(ウィーン分離派)の影響、さらにはバウ・ハウスのモダンデザインからの影響などを語らざるを得ないだろうし、またロンドンに渡って以降、バーナード・リーチからの直接的な指導への受容と反発は良く知られたところだ。
しかし今回あらためて概観して気づくのは、中国陶磁器、宋時代のものからの強い影響を感じることで、東洋美術とモダンデザインのクロスについて深く考える契機になったのは良い体験であったと思う。
過去に記述してきたことでもあるのだが、彼女が女性陶芸家として多くの優れた作品を遺すことができたのは、モダンデザインの勃興期に青春期を送り、そのデザイン史上若々しくも激動の時代の息吹を受け、造形感覚、色彩感覚を洗練させることができた人だったということでもあるが、何よりもそれ以前に「器」へのつきない興味と、技法への限りないチャレンジ精神のたまものであったのだろうと思う。
まず、土と、ろくろがそこにあったのだ。
またそうした精神力の源泉はナチス支配から逃れ、亡命ユダヤ人として生きるというある種の強いられた人生にも、希望を失うことなく日々を生き抜くという強い女性ならではのものがあったのだろうと思う。
![芸術新潮 2010年 06月号 [雑誌]](http://ecx.wp-content/uploads-amazon.com/wp-content/uploads/I/41rL-HJ3kZL._SL160_.jpg) 『芸術新潮』が今回の展覧会に併せ特集を組んでいる。
『芸術新潮』が今回の展覧会に併せ特集を組んでいる。そのタイトルは「ルーシー・リーに会いたい」とあった。
叶えられないものとなってしまったが、今、ボクはほんとうに彼女に会いたいと思う。
展示会場内にはいくつもの彼女の写真が貼られているのだが、ハイド・パーク近くの自宅兼工房で近所の人を迎え入れては手作りのケーキと紅茶を呈し、笑顔で語りかけるかわいらしく魅力的な姿がそこにはあり、それらは激動の20世紀を良き人生として生き抜いた一人の女性を映し出して見事であった。

なお、本展に続いて、以下のところを巡回する。
【ルーシー・リー展】巡回予定
■ 益子陶芸美術館:2010/08/07〜09/26
■ MOA美術館:2010/10/09〜12/01
■ 大阪市立東洋陶芸美術館:2010/12/11〜2011/02/13
■ パラミタミュージアム:2011/02/16〜04/17
■ 山口県立萩美術館・浦上記念館:2011/04/29〜06/26
また「ハンス・コパー展(20世紀陶芸の革新)」という展示企画が今週末から開催されるので併せて紹介しておこう。(ハンス・コパー:ドイツからの亡命ユダヤ人の陶芸家で、1946年から10数年間、共に作陶の日々を送る。その間数度の「二人展」を開催)
【HANS COPER ハンス・コパー展 20世紀陶芸の革新】
開館期間:2010年6月26日(土)〜2010年9月5日(日)
10:00〜18:00
休館日:月曜日[7月19日、8月9日は開館]、
8月12日(木)〜8月16日(月)
主 催:パナソニック電工 汐留ミュージアム、日本経済新聞社
写真中:《ブルー掻き落としの花生》1968年(shizuoka Art Gallery展図録より)
写真下:《溶岩釉大鉢(マーブル)》1979年(『芸術新潮』特集より)

 木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。
木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。
