2013年が開けました。
賀詞を交わすほどのめでたさなのか、今年に限っては浮かれ気分になれないという現実もありますが、三が日ほどは許していただきましょう。
今年は工房設立から数え、25周年になります。
四半世紀という時間の蓄積が、果たして木工家具制作において、長いものなのか、いやいやまだまだ短いのか、評価は様々でしょうが、本人にとってみれば、多少の感慨もあるというものです。
私はこの世界に入るのがかなり遅かったということもあり、同世代の著名な木工家が華々しく活躍しているのを横目で眺めながら、後塵を拝しつつも、がむしゃらに駆け抜けてきたというのが、この四半世紀でした。
木工家具制作というものを生業とするには、いくつかの条件が整わねばなりませんが、工芸という分野の中にあっても、木工について考えますと、技法の集積、修練というものが、その素材の特有性(自然素材としての扱いにくさゆえの)から、かなり大きな領域を占めているのは間違いないところです。
これは一朝一夕に習得できるものでないことも確かですが、しかし時間の蓄積が保証してくれるという性格のものでもあるのです。
無論、その過程では職業的厳しさを課すこと無しではダメですし、良い指導者、良い教育環境に恵まれるといった事なども欠かせぬ要素かも知れません。
しかし、脇目もふらず、真摯に取り組めば、相当程度の技法、技能は習得できるものです。
次なる必須の条件、デザイン力、独創力、あるいは制作したものを、テキストとして編集し、画像としてリタッチし、プレゼンテーションする能力というものも必要となります。
これらは、経験的蓄積も無為とは申しませんが、どちらかと言えば、木工以前のモノ作り共通とも言える、造形力、美意識、あるいは誤解を怖れず言えば、教養といった分野のもので、いわば能力+センス、あるいはモノ作りがいかに自身の人生にとって魅力ある対象であるか、どれだけ好きなのか、といったところに還元されるような性格のものなのかもしれません。
これらの物言いは、修練期間が短い、手業も決して十分でないかも知れない若輩の正当化のための物言いになってしまったかもしれません。
実はそれらの評価については、モノ作りというものの特異性によって担保されます。
どういうことでしょうか。・・・その作り手の能力は言うまでも無く、美意識、センス、さらには教養までもが露わに体現されてしまうのが、モノであるからです。
私たちモノ作りに勤しむ者に与えられた特権といって良いかも知れません。
作り手が何を語ろうと、あるいは周囲がどのようにその人物を語ろうとも、絶対的対象としてのモノがあるかぎり、それらは無効でしか無く、全てはモノに体現されてしまうという、怖ろしい現実、あるいはありがたい絶対性がそこにあるというわけです。
つまり私が何を語ろうとも、モノが全てを語り、どれだけの人にそれが正しく届けられるか、ということで決せられてしまうというわけです。
さて、こうしたモノの怖さと、それだけに魅了されるものだと言うことをを知ってしまった四半世紀の蓄積に踏まえ、また今年から新たな一歩を歩み出していきたいと考えています。
今年は個展も考えていますが、他、まだ明らかにできる段階ではありませんが、ある企てもあり、私の木工人生にとっては大きな転機になるやも知れません。
もちろん、良いモノ作りと、広く木工家具を届けるためへの新たな踏み出しです。
冒頭チラと触れたように、日本社会の困難さについては、ここでは多くを語りませんが、実に多難な時代に差し掛かっていることはどうも間違いないところのようです。
そうした状況にも、決して逃げる事無く、人が人として尊厳ある生き方ができる社会を築き上げるための寄与にも尽力したいと思いますし、仕事に関わる領域での若い木工志願者へのサポートも惜しむこと無く提供したいと考えています。
そうしたことを成し遂げるためにも、良い仕事に専心し、そこから人々との新たな繋がりを求めていくことも欠かせない基本的な要諦です。
どうぞ、2013年、工房 悠の活動にご理解いただき、ともに良い暮らしと社会を作り上げていきたいと願うものです。
ありがとうございました。 杉山 拝

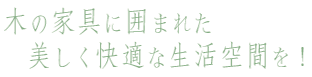


 054 631 4471
054 631 4471
2 Responses to “新春のお慶びを申し上げます”
開けましておめでとうございます
早々の賀状ありがとうございました。
今年は個展のお話もあるとのことですが、
ぜひご案内くださいね。
本年もどうぞよろしくお願いします。
岩瀬さん、コメントありがとうございます。
どんな新年をお迎えでしょうか。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
また連絡させていただきます。