梅雨入りに
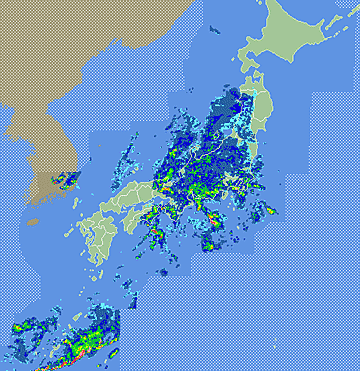
梅雨入りである。
例年よりも幾分遅い梅雨入りとのことだが、この季節を忌む者の一人としては一日でも遅れてくれることを望んでいたというのが本音だが、日本列島に住まわせてもらっている手前、この気象から逃れられるわけでも無し、頭が重くなり、手が鈍くなり、気が滅入ってくる。
ボクは精神的な疾患を抱えているわけでもないので、滅入る程度で堪え忍ぶこともできるがわけだが、こうした過剰とも思える湿潤な大気に病を悪化させてしまう人も少なくないのではと思ったりする。
ところでボクが好んで観る映画にトラン・アン・ユン(Tran Anh Hung)というベトナムの監督のものがある。『Mui du du xanh〈邦題:青いパパイヤの香り〉』、『Mua he chieu thang dung〈邦題:夏至〉』といった名作で著名な監督だが、あの独特のめくるめく官能的で瑞々しい映像美は、まさにアジアだなぁ、とつくづく感じ入ってしまう。
この“瑞々しい”だが、これが実は“水水しい”とでも意訳したいほどにウェットな大気がもたらすところの美質なのである。
エドワード・サイードの『オリエンタリズム』ではないが、同じアジアの日本のボクが観ても日本人が失ってきているかもしれないアジアに暮らす民衆のエートスがそこにはあるのかなと複雑な気分に陥ることも確かなこと。
つまり欧米人の目に映る東洋への眼差しのごとくにボクらの視点にも位相差ができてしまっていることへの戸惑いである。
あえて断るまでもなく、日本というものがやはりこうしたところにおいてもいかに特異なものであるかということを確認させられるというわけだ。
トラン・アン・ユンの映画が彼の国でどのように受容されているかは知らないし、また近代化へ向けて急速に発展しつつあるベトナムでは、彼の描く世界がどれだけ残存しているのかにははなはだ疑問もあるわけだが、雨期と梅雨というものが気象学的に大きな差異があるとはしても、かつての日本では、梅雨の時季の受容のされ方も今の時代とは違い、その凌ぎ方、もっと言えばその楽しみの在り様というものも多様にあったのかもしれないと思ったりする。
木工職人も昔であればふて寝して遣り過ごす、いやいや、恐らくはもっと別の楽しみを探し出してきては楽しむ、という町民文化のようなものがあったのではないかと思う。
あくせくするだけが人生ではないし、この時季であればこその楽しみを見いだし、それがまた木工へ向かうときに新たな豊かさを付加させるものになったりするというわけだ。
‥‥ っと、と。
しかし遣るべき事はしなければならない。
この時季、最優先させるべき仕事は、桟積みの材木の屋根の整備。
今では既に、死ぬまでに使うだろうと想定される材積は確保されているが、しかしその後も良い丸太があるとの知らせに胸躍らせる家具職人の宿痾は衰えることなく続くという結果、桟積みの山がいつまでも残る。
梅雨入り直前の日曜日、この桟積みの屋根の補強作業を行った。
最盛期と較べれば山の数は数分の一に減ってきたとは言うものの、乾燥を待つ材木がこの厳しい梅雨の時季を凌ごうとしている。
材の乾燥は木の仕事において、最重要な課題の1つ。
これがいい加減だと、大変な目に遭う。
先の松坂屋での個展がそれだった。


 木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。
木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。
