DOMINO 活用でらくらく2枚ホゾ
角ノミ盤を補うDOMINO
震災復興の態様の数々、フクシマを巡る「衆院東日本大震災復興特別委員会」の議論、気懸かりのことばかりだが、日常の業務は業務として進捗していく。あるキャビネットの中仕切り板の接合をどうするのか。
うちの場合、キャビネットの構造は框組み(かまちぐみ)が多いのだが、今回は板で指す構造。
無垢の中仕切り板を天と地、前後それぞれ2枚ホゾで指す。
このホゾ穴は角ノミで穿つのが望ましいのだが、板指しの場合は角ノミ盤の懐の制約上、できない相談。
こうしたケースで威力を発揮するのがFestool社の「Domino」だ。
好きなところに、好きなだけホゾ穴(様のもの)を穿つことができちゃう。
あえて問題を挙げるとすれば、角ノミのようにホゾ穴が角にはならず、ボーリングでのスライド加工になるので、末端が半円となること。
ま、これはホゾの方をテキトーに丸くしてやれば良いだろうし、逆にDomino穴を四角く補正すればなお OK ! ‥‥完璧だ。
つまり、Domino標準の平ダボを使うのではなく、板そのものからホゾを作るという前提なので、そのような方法を取る。
ただ“テキトー”が許されるとはいっても、板厚方向では寸法精度をしっかりと確保するということが条件になるだろうし、また前後のそれぞれ2枚のホゾを除く中央部には、小穴を突き、ここに大入れでメチボソを埋め込む、という方法で接合度、および、位置精度を確保することも欠かせない条件となる。
人によっては、前後に2枚ホゾでは済ませず、全ての領域にホゾを設けるという律儀な人も少なくないと見るが、中仕切りという構造上の位置づけからすれば、一般にはそこまでは求められないと考えている。(違いますかね?)
角への補正
このケースでは、基本の巾、左右のビット中央までの距離(イラスト参照)、13mmにビット径10mmを加えた数値、23mmの巾になる。
今回の中仕切り板の厚みは24mmであるので左右の端末を手ノミ一発で補正すれば良い。
片方は小穴が既に空いているので、それに手ノミを沿わせて打ち込めばよいし、反対側は白書きで墨を入れておけば1発で高精度な角穴が空く。
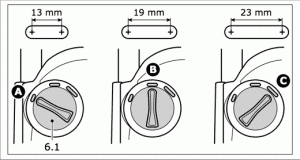 このDomino、機構上、1つのビットは、固有の巾で穿たれる以外に、他2種の巾で穿つことが可能(イラスト参照)。
このDomino、機構上、1つのビットは、固有の巾で穿たれる以外に、他2種の巾で穿つことが可能(イラスト参照)。
例えば、10mmのビットの場合、23mm以外に、29mm、33mmという巾の穴が穿たれる。
同様に、他のビットでは以下のよう。
- Dominoビット、5mm:18mm、24mm、28mm
- Dominoビット、6mm:19mm、25mm、29mm
- Dominoビット、8mm:21mm、27mm、31mm
- Dominoビット、10mm:23mm、29mm、33mm
これらの寸法を駆使すれば、様々な板厚に対応できるということになるわけだ。
(ただもちろん、任意の巾にはできない)
こうした方法の具体的なプロセスは、あえて書くまでもないことだが、以下簡単に記述しておく。
- 被加工材への墨付け(ホゾ位置のセンター、つまり左右方向、および奥行き方向、2つのセンター)
- 2枚の位置決め治具
- (左右方向)Dominoの中央部に墨線が来るように、被加工材の末端からの長さとDominoフェンスの巾から導き出される寸法の差尺で合板などをカット(画像の a )
- (奥行き方向)被加工材末端から墨線までの寸法から10mm減じた巾のものを合板で作る(画像の b )
- 被加工材にそれぞれのジグをしっかりと固定して、あとはDominoをジグにぴたりと合わせて開ける。
- 2枚ホゾの場合は、その差尺の介モノを挟めばOK !
DOMINO、再びの賞賛
ところで、こうしたDominoなどが開発される前は、懐の深い角ノミを自作しようかと真剣に考え、設計し、鉄工所に見積もらせたことがあった。
しかしその剛性の確保、あるいは十分な使い勝手のものを製作するのは、かなり困難であることにぶちあたり断念するということがあった。
またビスケットジョインター、Lamelloを用いるという方法もあるのだが、これはホゾという接合システムとは似て非なるものであり、代替できるものでは到底あり得なかった。
そこへDominoの登場とあいなり、それまでのモヤモヤした悩みは一蹴され、クリアな世界が拡がったというわけだ。
Festool社にはひとりの家具職人として、ホントに感謝をしている。
このDomino、リリース後、既に4年が経過するものの、いまだに他社が追随するという気配はない。
発売当時、その価格があまりに高いということで敬遠される向きも強かったようだが、国内正規ルートでも現在はおおよそ当時の半額程度で流通していると聞く。
海外での購入ルートがある人は、より廉価に入手することが可能なわけだし、そうした価格訴求の側面からも、コピーが上手と思われる国内メーカーも、その開発には二の足を踏んでしまっているのかもしれないね。
発売当時、FWW誌にはこのマシンを指し、惜しげもなく「INNOVATIONS」と評価し、「the Domino is an impressive tool that could change your woodworking.」と、唆してもいた。
様々なホゾ穴の加工機械を、アングルグラインダー様の駆体の中に封じ込めるという荒技。
ボクは国内ではまったく情報が無かった段階の2007年2月、Festool社のWebサイトではじめて発見し、その姿、機能にはホントに驚き、小躍りせんばかりに興奮した。(What’s DOMINO ?)
電動工具の世界で、このように興奮させるのは恐らくはこのDominoが最初にして最後かも知れないとさえ思えてくるほどだ。
手ノミについて
さてところで、角穴にするための手ノミ作業について、1つ付言しておこう。
うちの手ノミは、角ノミに合わせて製作してもらっている。
つまり、以下のようなラインナップ。
3mm、4.5mm、6.4mm、8.0mm、9.5mm、11mm、15mm,といった具合。
これは説明するまでもなく、ホゾ穴は角ノミで穿孔するのが一般となっているので、それに合わせただけのこと。
そうした方法に準じるのであれば、Domino導入に合わせて、10mmというサイズも作っておこうかな。
メチボソが汚いけれど、ご愛敬。ルータービットでカットしたものだが、ちょっと切れが切れてきている。ここは入り面を取るので、無視して差し支えない。
因みにメチボソの小穴は丸鋸昇降盤でのカッター加工(ハンドルーターなど使うよりも圧倒的に安全、高精度、高作業性、高切削肌)
梅雨時にこんな板指しの仕事などするもんじゃないのだけれどね(苦笑)



 木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。
木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。

acanthogobius
2011-6-1(水) 17:20
こういうのをメチボソと言うのですね。
2枚ホゾの一部に切り込みが入ってしまっているのは
メチボソを加工する時にチップソー(またはカッター刃?)を
通した跡、と理解して良いのでしょうか?
で、これは接合強度には影響しないという判断ですか?
artisan
2011-6-1(水) 20:47
acanthogobiusさん、見て欲しくないところを集中的に責めてきますね〜。
aboutな機械加工がバレバレじゃないですか。
まぁ、この程度(いずれも数mm)の鋸目は無視できる範囲ということで‥‥。
(重要なのは胴付き[ライン]の精度、追い入れ[メチボソ]の寸法精度の方ですから)
でもよい子の皆さんはしないように‥‥
因みに小穴は3分(9mm)
(やり過ぎた)丸鋸加工で残ったところは、ピンルーター、その後、手ノミで仕上げというプロセス。
〈メチボソ〉という呼称は、職人の符牒のようなものですね。
一般には「追い入れ」とでも言うのか知らん。
こういう画像(失敗を晒しても)というものは、一般のテキストには無いと思われるので、あえて掲載。
acanthogobius
2011-6-2(木) 12:39
artisanさんの、このブログの写真はいつも穴が開くほど(笑)
眺めているので分かりますよ。ありがたいことに拡大画像も付いていたし。
aboutだとは思っていません。仰るとおりテキストにはないので
参考にさせていただきます。
artisan
2011-6-3(金) 00:02
acanthogobiusさん、あなたはこのBlogの最良の読者の一人であることは確かなことですので、求められる記事の品質には応えていきたいところですが、日々の仕事ならではの舞台裏も晒してしまうということでもあります。
(画像サイズ、小さくした方が良いかも、ですが‥‥)